専門コラム 第21話 成功への導線を計画的に決めて、最高の気分に浸る。
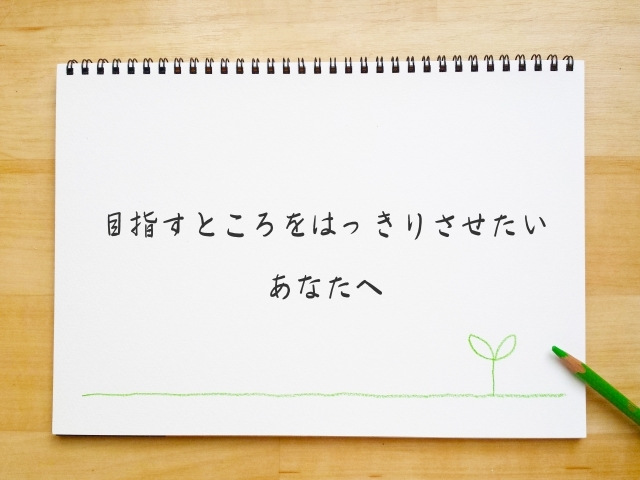
目指すべきところに志はあるか
どこに行きたいのか分からなければ、目的地に着いても気づかない。
アメリカのコンサルタント、レスリー・ヤークスの言葉です。
ヤークスといっても馴染みがないかもしれませんが、チャールズ・デッカーとの共著「ビーンズ!」で一躍有名になりました。
「ビーンズ!」は実在するシアトルのカフェを舞台にしたビジネスノンフィクションです。
徹底したプロ意識とたゆまぬ努力で、さまざまな逆風を切り抜けながらカフェを伝説のお店に育て上げた夫婦の取り組みを丹念に追っています。
「ビーンズ」には、冒頭の言葉を少しかみ砕いたこんな言葉もあります。
何を目指したいのかが曖昧なままでは、高い成果など上げようがない。成果はどれも、目標と比べてみてはじめて測れるのだから。目標に見合った成果が得られてこそ、『成功』という名の終着駅にたどり着いたと言えるのです。
あなたが「目指すところ」というのは、言い換えれば目標のことでしょう。上の言葉でもそういう使い方をしています。どんなことでもそうですが、特にビジネスにおいては目標設定が欠かせません。
目標設定で大切だと言われるのが「SMART」です。
- S=Specific 具体的である
- M=Measurable 測定できる
- A=Agreed upon 同意できる
- R=Realistic 現実的である
- T=Timely 期限がある
目標は、具体的かつ数字で測れるものであり、自分で納得でき現実的であって、達成期限を明確にしたものでないといけないということです。
それはそれで納得できます。
しかし、ただ単に、目標が到達すべき地点や数字というだけでは面白くありません。
自分の価値観や生き方に沿ったものでないと、十分な満足感は得られないのではないでしょうか。
達成したときに「自分が求めていたものはこんなことではなかった」というような虚しさが湧いてくると思いますし、そもそもモチベーションが保てるかも疑問です。
そういう意味で、目標とは「志」と言い換えられるものであるべきではないでしょうか。
心を高揚させる勝利のために
「ビーンズ!」が多くの人に受け入れられたのは、単なるサクセスストーリーではなく、その道筋の随所に人の心を第一に考えてきたことがうかがえるからです。
お店は顧客に愛され、可愛がられなければたちまち潰れてしまいます。
同書は、そのためには、そこで働く人に愛される店でないといけないと強調します。
従業員が店を愛していれば、いい店にするため、お客様に喜んでもらうためには何が必要かを自分で考えます。
そして、商品の質を高めたり、心からのサービスを心がけたり、一人ひとりのお客様とコミュニケーションをとるようになるのです。
すると、お客様にとって店は、居心地のいい空間になり、ファンになってくれるといういい循環が生まれるのです。
さらに、こうした接客や雰囲気作りも含めて、店の強みを持つことだと指摘します。
ファンになるお客様は必ずその強みを見出し、リピーターになってくれるだけでなく、お客様自身が顧客を広げていってくれるというのです。
「ビーンズ!」では、仕事から満足と成功を得るために必要な五つの材料として、次の4P+Iを挙げています。
- 情熱(Passion)
- 人(People)
- 商売を超えた温もり(Personal)
- 商品(Product)
- 志(Intention)
ビジネスにおいて何を求め、何を目指していますかと問われたら、営業の人なら、大半が売り上げトップの座と答えると思います。
それは当然ですし、間違ってはいません。
しかし、商売の相手が人である以上、情熱や人としての温もりといったものがないと、こちらの思いは相手には伝わらないでしょうし、数字をあげたとしてもどこか満たされず、心は乾いたままという気がするのです。
「星の王子さま」で知られるフランスの作家、サン・テグジュペリはこう言っています。
心を高揚させる勝利もあれば、堕落させる勝利もある。
心を打ちひしぐ敗北もあれば、目覚めさせる敗北もある。
孫子の兵法の教え
目標の話に戻りましょう。
目標を設定すれば、次はその目標をいかに達成するかです。
計画のない目標はただの願い事にすぎない。
これもサン・テグジュペリの言葉ですが、目標達成のためには当然、ステップを踏んだ計画が必要です。
それは、ゴールへとつながる導線でないといけません。
そのためにはまず、現状を数字で把握することが求められます。
あなたが売り上げトップを目指すなら、いくらの売り上げが必要かをはじき出したうえで、現状との差を把握し、どうすればその乖離を埋めることができるかを考えるのです。
ただし、具体的な数字をあげなければなりません。
目標と現状の差を埋めるには1カ月でいくらの売り上げが必要か、そのためには何人の見込み客をつかみ、そのうち何人を成約に持ち込まないといけないか。
そのためには、何が必要か……。
ここで大切なのは、希望的観測にすがらないことが一つ。
もう一つが、お客様は将棋の駒でも騎手に操られた馬でもないと自覚することです。
お客様がこちらの思惑通りに動いてくれれば、それほど楽なことはありませんが、決してそんなことはありません。
ただし、それに近いことは可能でしょう。
お客様を自分のファンにすることです。
まさに、「ビーンズ!」のカフェが実践したことです。
以前に紹介した、中国古代史を題材にした小説の第一人者、宮城谷昌光の小説に「楽毅」という作品があります。
中国の戦国時代に覇を競った「戦国七雄」の一つ、燕の国の将軍として大勝を重ねた楽毅の生涯を描いたものです。
その中に、次のような一節があります。
孫子の兵法では、闘いというものを、武器と武器の衝突、城壁と雲梯(梯子車)の接触とはみなさず、人と人の争いであるという前提から、人とは何か、その人がつくる国家や軍隊とは何か、という洞察に主眼が置かれている。
孫子の兵法は、戦わずして勝つことこそ最良の勝ち方だとしており、楽毅は、だからこそ孫子の兵法は優れているというのです。
孫子の兵法には、現代でも折りに触れて活用される有名な言葉がたくさんあります。
彼を知り己を知れば、百戦して危うからず
善く戦うものは人を致して人に致されず
善く戦うものは、勝ち易きに勝つ者なり
1つ目はあまりにも有名ですね。
2つ目は主導権を握り、それを放さないことです。そのためには、確たる目的や戦略・戦術を持って、臨機応変に対応しなければいけません。
3つ目は、相手の反応を想定して先手先手で動いて、水が自然と本流に流れ込むように、いつのまにか成約にもっていくということになります。
いずれも、人の心の動きに敏感になり、何手も先を読むことの大切さを指摘していると言えます。
あなたも目指すところをはっきりとさせたうえで、成功への導線を計画的に決めて売り上げを飛躍的に伸ばし、最高の気分に浸りたくありませんか? ?
