専門コラム 第81話 土地探しの注意点「ハザードマップ」と「コンパクトシティ」について

土地込みで計画を進めている方を担当する場合に限らず、敷地に関する法規制の理解は、住宅営業についた新人さんが真っ先に身につける基本知識です。
ただそうした基本知識に加え、新たに習得をおすすめしたいものに、地域の災害予見と立地適正化計画への理解があげられます。
たとえば直近で発生した「令和 2 年 7 月豪雨」は、いまや熊本に限らず、日本のどこに発生してもおかしくない自然災害でした。
近年ではこのクラスの豪雨災害が、年に数回程度、どの自治体でも起きており、一定数の死者や行方不明者を出しています。
こうした状況を考えても、ハザードマップ(災害予測図)を活用した土地選びは、もはや必須と考えていいと思います。
一方で、日本も本格的な人口減少の時代に突入し、自治体の都市計画が立地適正化計画に進んでいることも見逃せません。
もちろんこれらの知識も、基本的なことは住宅営業なら押さえておくべきです。
今回はこの二つについて、まとめてみましょう。

土地探しの注意点「ハザードマップ」と「コンパクトシティ」について
住宅営業も事前にハザードマップで災害リスクを把握しておこう
住まいの計画を土地購入から進めなければいけない方も多いでしょう。
その際、災害リスクをそれほど考慮せず、土地選びを進めていた時代が以前ならありました。
しかし現在は、水災害や震災など自然災害を想定し、土地選びを進める事が、半ば当たり前になっています。
しかし当の不動産会社の対応はどうも一律ではないようで、ハザードマップの資料添付や具体的な説明義務なども、現状では法的にも必要ないようです。
この辺のところは、以前本コラムでも紹介している、ふくろう不動産の動画[1]「不動産の売買契約時にハザードマップの説明は法的に不要という話は本当ですか」が、非常に参考になります。
この動画でも伝えられているように、土地の購入者は売買契約を結ぶ以前の段階(あるいは重要事項説明の前段階までに)で、ハザードマップでどのようなリスクが起きそうか、あらかじめ調べておいた方が安全でしょう。
また不動産機能がない建築系の営業も、敷地調査報告の場やお客様と一緒に土地選びを進める際、当該敷地の自然災害リスクをハザードマップ等で調べておくことは、土地選びのアドバイスの点からも必要なことです。

参考サイト [1] [不動産の売買契約時にハザードマップの説明は法的に不要という話は本当ですか](https://www.youtube.com/watch?v=F5iIi8pzdGA)
ハザードマップポータルサイトと防災対策にも使える地理院地図
ハザードマップは国土交通省が運営し、自治体のものとも連動している「ハザードマップポータルサイト[2]」が有名です。
「ハザードマップポータルサイト」のページを開くと、左側の全国版に「重ねるハザードマップ」という薄いピンクで象られたゾーンがあります。
そこの「地図を見る」か「場所を入力」すれば、説明のとおり、災害のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを、地図や写真に自由に重ねて表示できます。
なお全国版の表示する情報については、「洪水」と「土砂災害」を押さえておけば大体間違いありません。
右側の地域版は主にPDF版で示され、洪水ハザードマップや火山ハザードマップなど、指定したマップをそれぞれ表示できます。
つまり全国版と地域版との大まかな違いは、「重ねるハザードマップ」として使えるかどうかということになるでしょう。
また防災対策にも使える「地理院地図[3]」は、本家のハザードマップより表示もきれいで、且つ便利に使えます。
「地理院地図」は国土地理院が作成したもので、いわゆるハザードマップではありません。
しかし学校教育に役立つように作られただけあって、地図から読み取れる情報も多く、使い勝手も良好です。
「地理院地図」をハザードマップがわりに使っている方もいますから、この 2 つをおさえておけば大体間違いありません。
時間があればぜひ試してみてください。
(なお今回の「令和 2 年 7 月豪雨」では、河川の氾濫だけではなく、用水路からの浸水も見られたようです。このためハザードマップも根本的な改善が求められます。)
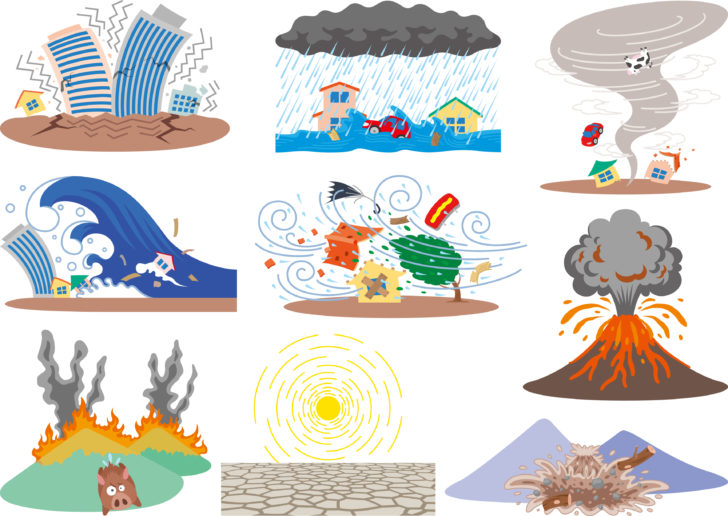
参考サイト [2] [ハザードマップポータルサイト](https://disaportal.gsi.go.jp/)
参考サイト [3] [地理院地図](https://www.gsi.go.jp/top.html)
「20 年後の暮らし方をイメージする」立地適正化計画の活用
立地適正化計画とは、住民の居住形態や、主にそれを取り巻く医療、福祉、商業、公共交通等の施設誘導を中心市街地や駅周辺(或いはその他の特定地域)に促し、より人口減少社会に見合った都市計画を推進することを言います。
人口減少社会といっても、自治体によっては、まだ人口が増え続けているところもあります。
ただ地方都市の多くは、人口減少の一途を辿っています。
そのため立地適正化計画の進度は地方都市のほうが早く、富山市や北海道の鷹栖町などの「コンパクトシティとしての成功例」も、早い時期から出ていました。
したがって多くの自治体では、立地適正化がすでに計画上は出来ており、各市区町村の状況に応じて、必要な計画が(目に見えないレベルではありますが)進められています。
では、立地適正化計画が「土地探し」にどのような影響を及ぼすかですが、10 年から 15 年といった比較的近い将来というより、20 年後にどのような生活をイメージできるか、より長期的なスパンで考えてみるのが良いでしょう。
20 年後をイメージすることは難しいかも知れません。
ただ人口減少化は首都圏でも必ず到来していると考えられます。
その際、自治体の行政サービスを受けたと想定したとき、住宅を建てるための土地を郊外の外れに求めるのではなく、街の中心地に求めたほうが、将来的には間違いの無い土地選びをしたことになりそうです。
マイカーの自動運転化が進むから、それほど立地適正化計画は進展しないのではという見方もあります。
ただ自動運転化が、どれだけ私たちの生活に溶け込むかは分かりません。
地方都市ではイメージしにくいかもしれませんが、首都圏ではクルマを所有しない世帯は、徐々に当たり前になりつつあります。
つまり限られた財源で、効果的な行政サービスを提供するとなると、 これまでの拡散型の立地計画では 、追いつかなくなる可能性があります。
そのため生活地域や公共交通網を、可能な限りコンパクトにまとめる。
これが立地適正化計画の基本的な考え方です。
これらを踏まえて、土地選びをアドバイスすること。
こうしたことが、これからの住宅営業に求められていることは、意識しておかなければならないでしょう。
